循環型社会とは...
循環型社会とは、資源の有効活用を推進するためのモデルだと考えてください。
たとえば、日本国内における「日本における物質のフロー」では、投入資源(総物質投入量)に対して資源循環は1割程度しかありません。もし、資源に限界があるとすれば、天然資源等投入量は減少しますから全体を圧縮するような資源の利用をしなければならなくなります。それには、現在のような消費型の社会を見直す必要があります。
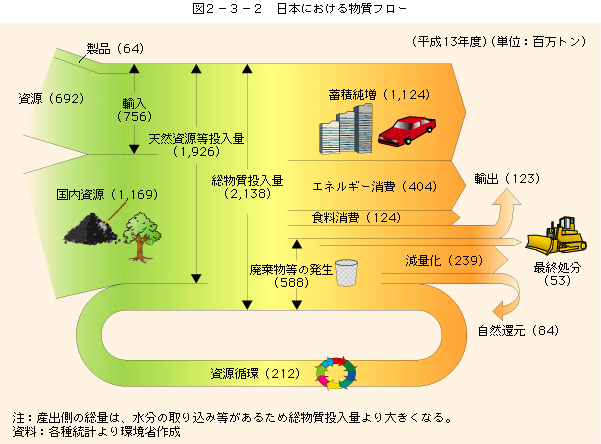 環境白書平成16年版より
環境白書平成16年版より
漠然と「消費型社会の見直し」といっても、なかなか感覚的に理解しづらいので、この一番身近な例として、PETボトルで、説明してみましょう。
清涼飲料などに使われているPETボトル(透明なPETボトルなどの指定表示製品*)のほとんどが、コピー用紙でいえばバージンパルプと呼ばれる木材から生産されたコピー用紙と同じで、天然資源(この場合ですと石油)からの製品です。
では、PETボトルのリサイクルとは、何にリサイクルされるかというと、洗剤やシャンプーなどのボトル用PETボトルや繊維などに用いられます。このようなリサイクルは、マテリアルリサイクルと呼ばれます。
この部分では、PETボトルの資源循環はされているように思えますが、指定表示製品を市場に投入する限り、その原材料となるのは、リサイクルされたPETボトルではなく、新たに投入される資源であるということです。極論ではありますが、我々が普段街中でPETボトルの飲み物を飲むたびに、新たに資源(つまり石油)を投入するということです 。「市場に常に新たな天然資源を投入することを前提にしたシステム」を、『リサイクル』とはいいがたいのではないでしょうか。
現在、一部市場には、「PET to PET」(指定表示製品からリサイクルされた指定表示製品)が流通していますが、ごく一部でしかありません。その理由は、そのための施設(プラント)や回収率などのコスト面などの問題があるからです。
|
|
循環型社会の理想的な形は、図の例でいえば、緑の枠で完結することですが、現実問題としてこれは不可能でしょう。 (品質の保持の限界や、回収率などの課題のほかに、再生にかかるコストなどの問題があります) そこで、可能な限りではありますが、緑の枠の中で循環できるようにする試みが必要です。 その第一歩が、リサイクルのための分別収集です。 「捨てればゴミ、分ければ資源」 この言葉が、一番よく表現しているのではないでしょうか。 日常生活や企業をはじめとした経済活動において、完全なゼロエミッション(排出物をなくす)は、現実的ではなく、むしろ、「最終処分量をいかに減らしていくか」、「資源として活用していくか」が今後の課題であり、循環型社会の目的でもあります。 |
指定表示製品:
分別回収をするための表示をすることが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品のこと。 (分別のための表示であって、環境に対しての表示ではありません)
PETボトルの場合ですと、![]() マークがついている製品をさします。
マークがついている製品をさします。
ありがちな勘違い?
![]() マークの数字『1』は、資源の利用回数を表示していると、勘違いしていませんか?
マークの数字『1』は、資源の利用回数を表示していると、勘違いしていませんか?
マークの中の数字は、素材についての表示でしかありません。
前述したように、分別のための表示であり、リサイクルの頻度を表すものではないのです。
 |
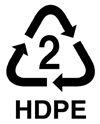 |
 |
 |
 |
 |
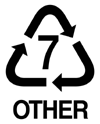 |
| ペット樹脂製品 | 高密度ポリエチレンを使用した石油製品 | 塩化ビニール樹脂を使用した石油製品 | 低密度ポリエチレンを使用した石油製品 | ポリプロピレンを使用した石油製品 | ポリスチレンを使用した石油製品 | その他の石油製品 |
ペットボトル ビデオテープ |
レジ袋・バケツ・お弁当箱 | ラップ・パイプ・ホース | ラップフィルム ポリ袋 |
食器容器 収納容器 |
トレー・植木鉢 おもちゃ |
参考までに、PETボトルからの再生品(マテリアルリサイクル)には、![]() マークがついています。
マークがついています。